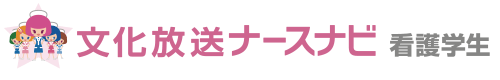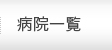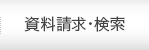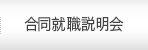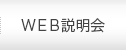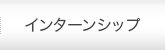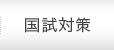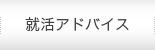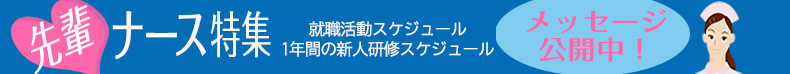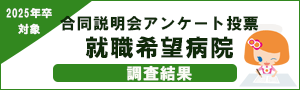文化放送ナースナビ看護学生 TOP > 先輩ナース特集 >

エラー
| 存在しないデータです。 |

社会福祉法人聖隷福祉事業団 浜松市リハビリテーション病院
〒433-8511 静岡県 浜松市中区和合北1丁目6-1
- 病床数/225床
- 診療科目/内科・整形外科・リハビリテーション科・歯科
- 看護方式/チームナーシング・プライマリーナーシングの併用体制
- 看護配置/一般病棟 15:1
回復期リハビリテーション病棟 13:1