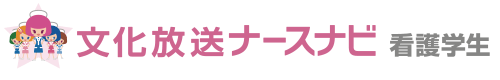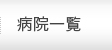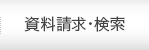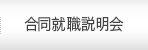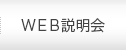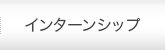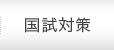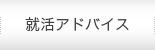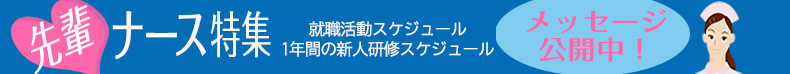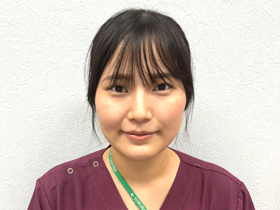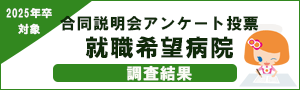Profile

- 氏名
- S・O
- 病院名
- 横浜市立大学附属市民総合医療センター
- 所属診療科目
- 救命センターICU
- 役職・資格
- 看護師
- 卒業学校
- 東京医療保健大学
- 卒業年
- 2022年卒業
入職を決めた理由
災害看護や救急看護に興味があり、三次救急、YMATとしての活動ができる病院を探しました。その中でも大学病院である当院は教育体制が整っており、初年度の豊富な研修だけでなく、2年目以降もレベルアップのために行える研修があります。そのため看護技術を磨き続けられることを知り、当院を選びました。
コロナ禍でありインターンシップの開催はしておらず、オンラインでの病院説明会に参加しました。その際に質問させていただいた先輩の雰囲気がとてもよく、当院で働くイメージができたことも理由の一つです。
病院選びで重視した点
[病院機能]
救急看護や災害看護に興味があったため、自身のキャリアを考えまずは急性期病院で経験を積みたいという思いがありました。その中で三次救急病院であるか、災害拠点病院であるかを一番重視して選びました。
[教育体制・看護体制]
救急看護、災害看護を希望しているものの、仕事についていけないかもしれないという不安もありました。そのため、先輩と密に関われるPNS看護体制をとっていることや、業務に必要な学習を院内研修、部署勉強会、OJTなど多様な方法で支援してくれることを知り、決定の大きな理由となりました。
[通勤のしやすさ]
電車が2路線あり、駅から徒歩圏内で通勤しやすい環境にあったことも良かったです。
就職活動スケジュール(いつどんな活動をしたのか)
[最終学年の前年]
■4月
病院の資料を集める
■8月
合同説明会参加(対面)
■11月
合同説明会参加(オンライン)
■12月
病院説明会に参加(3院程度)
■2月
オンライン説明会参加
[最終学年]
■4月
就職試験面接
■2月
国家試験
1年目に苦労したこと、嬉しかったこと、よかったこと
発語できない患者さんとの関わり方やご家族との関わり方に苦労しました。ICUでは気管内挿管をし人工呼吸器を使用している患者さんや気管切開をしている患者さんが多く、自分の意思を言葉にして発することのできない状況にある方が多くいます。そのため、その患者さんと言葉以外の体動や表情をどのようにして読み取れるのか、思考錯誤しながら患者さんと向き合っていました。また実習ではあまり関わることのない、重症患者さんのご家族との関わりもとても難しく感じました。
患者さんの容体が良くなり、人工呼吸器がはずれ、患者さんの声を聞くことができた時はとても嬉しかったです。
新人研修内容の特長
研修は必須の集合研修と部署研修があり1年間を通して多くの内容を学びます。またそのほか自身で選択して受講可能な研修も数多くあります。
1年目の集合研修では、実際に病棟内で使う物品を使用して研修を行います。そのため病棟に戻った際、すぐにその技術を活用できることがよかったです。
印象に残っているのは、入職しすぐの頃に受講したフィジカルアセスメント研修です。学生時代の知識を復習するとともに、実際に人を相手にしながら演習をする事で、知識のアップデートをする事ができました。またフォローアップ研修では他部署の新人と業務の習得状況や悩みを共有することで、自身の振り返りにもなり頑張る意欲へと繋がりました。
1年間の新人研修スケジュール
■4月
☆入職☆
部署配置
全体研修
病院概要説明
シャドーウィング研修
PNS研修
■5月
全体研修
フィジカルイグザミネーション
ME機器研修
■6月
Vライン確保研修
■7月
メンタルヘルス研修
■8月
多重課題の実践演習
■10月
メンタルヘルス研修ヘルス研修
■11月
遅出勤務開始
■12月
入院担当開始
■2月
メンタルヘルス研修

公立大学法人横浜市立大学 横浜市立大学附属市民総合医療センター
〒232-0024 神奈川県 横浜市南区浦舟町4-57
- 病床数/696床
- 診療科目/【疾患別センター】
高度救命救急センター 総合周産期母子医療センター リウマチ・膠原病センター 炎症性腸疾患(IBD)センター 精神医療センター 心臓血管センター 消化器病センター 呼吸器病センター 小児総合医療センター 生殖医療センター
【診療科】
一般内科 血液内科 腎臓・高血圧内科 内分泌・糖尿病内科 神経内科 乳腺・甲状腺外科 整形外科 皮膚科 泌尿器・腎移植科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 放射線科 歯科・口腔外科・矯正歯科 麻酔科 脳神経外科 リハビリテーション科 形成外科 病理診断科 臨床検査科 - 看護方式/PNS
- 看護配置/7:1