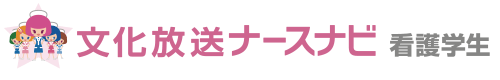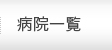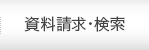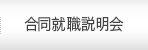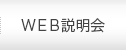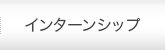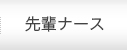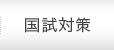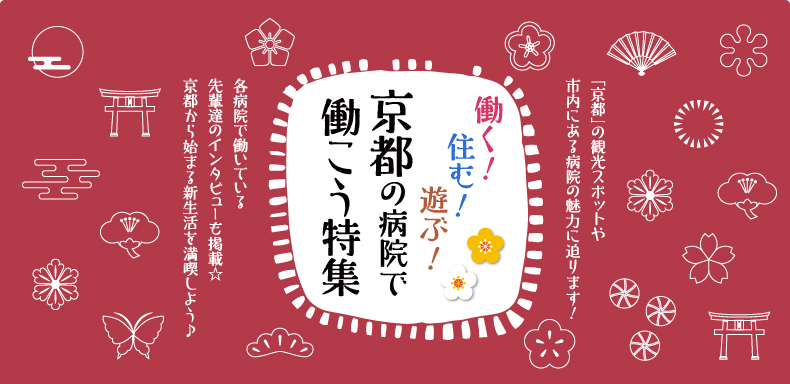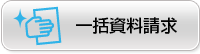-
京都MAP
より大きな地図で 京都特集 を表示 -
京都DATA
面積(2015年10月) 4,612km2 人口総数 (2016年9月)(推計) 2,605,423人 世帯総数 (2016年9月) 1,161,564世帯 病院数(2014年) 174 一般診療所(2014年) 2,459 看護師(2014年) 24,637人 准看護師(2014年) 5,659人 助産師(2014年) 903人 保健師(2014年) 1,087人
京都の観光スポット

-
清水寺
奈良末期778年に僧延鎮が開山し、平安建都間もない延暦17年(798年)坂上田村麻呂が仏殿を建立したと伝えられています。
春の桜と新緑、秋の紅葉と四季折々の美しさを背景にした懸崖造りの本堂(国宝)は、断崖の上にせりだし、市街地の眺望も最高です。あわせて15の堂塔(いずれも重要文化財)が建ちならんでいます。

-
衹園祭
衹園祭は八坂神社の祭礼で、大阪の天神祭・東京の神田祭とともに、日本三大祭のひとつに挙げられており、その歴史の長いこと、またその豪華さ、祭事が1ヶ月にわたる大規模なものであることで広く知られています。
祭のハイライトは17日と24日に行われる33基の山鉾巡行。「京都衹園祭の山鉾行事」はユネスコ無形文化遺産にされています。

-
渡月橋
渡月橋(とげつきょう)の南にそびえる標高375mの嵐山は美しい自然に囲まれ、桜と紅葉の名所として賑わいます。渡月橋はその嵐山の中心を流れる桂川(かつらがわ)に架かる全長155mを誇る橋です。

-
伏見稲荷大社
全国に約3万社あるといわれる[1]稲荷神社の総本社。
稲荷山の「千本鳥居」が有名な伏見の名所です。
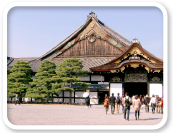
-
二条城
旧桂宮御殿を移した本丸(重要文化財)と豪壮な二之丸御殿(国宝)からなる。 京都市街の中にある平城。1994年(平成6年)にはユネスコの世界遺産(世界文化遺産)に「古都京都の文化財」として登録されています。

-
北野天満宮
北野天満宮は、菅原道真公(菅公)をおまつりした神社の宗祀(総本社)で、親しみを込めて「北野の天神さま」と呼ばれています。
毎月25日は御縁日として、終日境内周辺に露天が所狭しと立ち並び、参拝者の人波が絶えません。

-
平等院
永承7年(1052)、時の関白藤原頼通が、父 道長より譲り受けた別業を仏寺に改め、平等院としました。
約1000年前に建立された建造物や仏像が今に伝えられ、世界遺産にも登録されております。
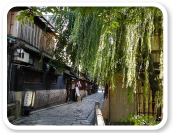
-
京町屋
京都市内のいたるところに昔からの町屋がたくさん残っています。
現在もその町屋が昔のままの価値を持ち続けているのが京町屋の特徴だと思われます。
京都は三方を山に囲まれた京都盆地の中にあり、寒暖の差が激しく厳しい自然環境に対応するため、京町家にはさまざまな工夫が凝らされてきましたが、これは日々の暮らしに内包された人と自然との共生の知恵でもありました。

-
旧壬生屯所(八木邸)
幕末、浪士隊として将軍家茂警護のため幕命により上洛するも分裂、その後松平容保お預かりの京都の警察部隊として再編された「新選組」。近藤勇を局長とする体制に落ち着いたころ、宿所としていた八木邸を新選組の屯所としました。隊士が増えて手狭になり西本願寺へ屯所を移すまでの間、この地を拠点にしていた間に、有名な池田屋事件がありました。お向かいには現在公開はされていませんが同じく新選組の屯所であった旧前川邸があり、西側には境内が兵法調練場にも使われた、新選組とも縁の深い壬生寺があります。[画像提供:幕末トラベラーズ]
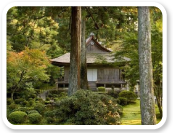
-
三千院
三千院は8世紀、最澄の時代に比叡山に建立された円融房がたび重なる移転を経た後、元々当地にあった往生極楽院(旧称・極楽院)をその境内に取り込む形で現在地に移ったものです。往生極楽院は12世紀に建てられた阿弥陀堂で、国宝の阿弥陀如来及両脇侍像(阿弥陀三尊像)を安置しています。

-
妙心寺
妙心寺は、全国に3400の寺院を持つ臨済宗妙心寺派の大本山です。その広大な境内には38、境外には10の塔頭があります。法堂(はっとう)の天井に描かれた巨大な雲龍図は、見る位置や角度によってその動きや表情が変化するため「八方睨みの龍」といわれます。